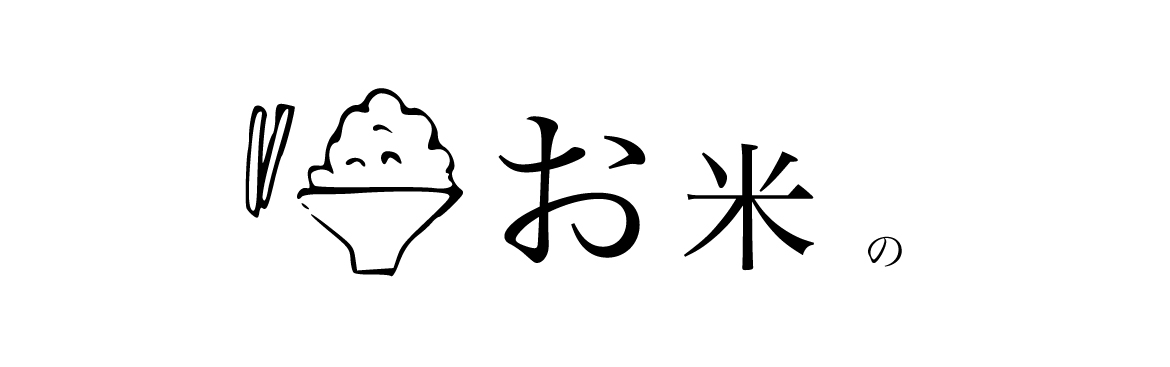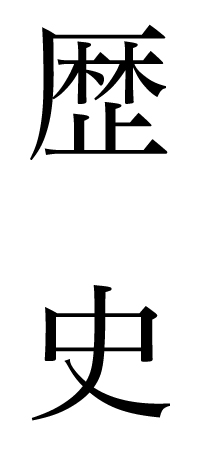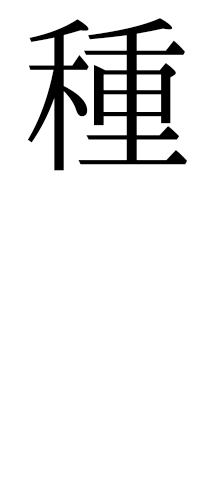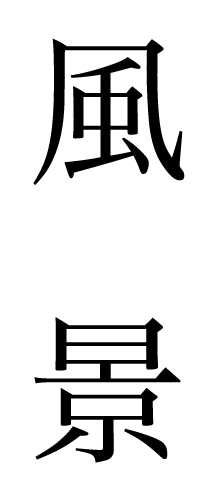お米農家なら知っておきたい!多くの品種を作り出した『交雑育種法』

偶然と自然の力を借り、長い時間と手間をかけて新品種を生み出す分離育種法は、各地でたくさんの重要な品種を生み出した。しかし、形質が固定された品種は劇的な突然変異でも起こらない限り、それ以上の新しい品種が生み出されない。より良い品種を求めて次に開発されたのが、形質の異なるイネ同士を掛け合わせる交雑育種法である。
イネの受粉システム
お米農家の皆さんはご承知のことと思うが、イネは自家受粉をする植物だ。自分の雌しべ(胚珠)と自分の雄しべ(花粉)で交配し、実をつける。モミが開花するのは天気の良い日の午前中、わずか数時間である。わずかにモミが開くとすぐに雄しべから花粉が雌しべへ降り注ぎ、あっという間に受粉が完了する。
このシステムは風や虫が他の個体の花粉を持ってきてくれるのを待つ必要もなく、確実に実を付けることができる効率的な機構だ。イネをただ育てるだけならば構わないのだが、これは異なる品種のイネ同士を交雑させようとすると大きな問題になる。開花してから雄しべを除去しても間に合わず、自家受粉が済んでしまうのだ。交雑育種が日本で始まったころは、開花前のモミに穴をあけ、まだ花粉を付けていない雄しべを1本ずつ取り除くという気の遠くなるような作業が行われていた。
昭和に入ると、イネの花粉と胚珠の耐熱性の違いを利用した『温湯除雄法』が開発された。花粉は胚珠よりも熱に弱く、お湯につけると受粉させることができなくなってしまう。雌しべを使いたいイネの穂を43度のお湯に数分つけることで、花粉だけをダメにしてしまうのだ。

根気強く行う人工交雑の流れ
交雑育種法によって新しい品種を作ろうとする場合、まず初めに考えなければいけないのは交雑の組み合わせである。一般的に、既存の品種の欠点を補うような掛け合わせを考えることが多い。例えば、『寒さに強く、味もよいが、病気に弱い』という品種があった場合は、耐病性のある品種と掛け合わせ、病気にも強いという新たな形質を持たせることを目標にする。交雑させる2種類のイネを確認したら、それらの株が同じ時期に花をつけるよう計算して栽培を行う。片方が受粉の準備万全なのに、もう一方が未熟では話にならない。早生品種と晩生品種を掛け合わせる場合は播種時期から調節する。
交雑を行う日、花粉を使う(父親にする)イネは開花した状態にしておく。胚珠を使う(母親にする)イネには温湯除雄処理を行い、花粉を無効にしてしまうとともにモミを開かせる。手作業で一つ一つ花粉をふりかけ、受粉は完了する。実ったら採取し、それを種として次世代を育て、目的とした形質を持ったイネができているかどうかを確認する。交雑が成功していそうな個体を選抜し、その後何世代か育て続けることで形質を固定させなければならない。試験栽培中に導入できたと思っていた形質がなくなってしまうこともある。
新しく作った品種が期待されるものであるか、生育に問題がないのか、実用に供するものであるかは長い時間をかけた試験栽培で初めてわかる。一つの品種ができるまで10年以上かかることもあるのだ。

日本における交雑育種法の歴史
明治36年、日本で本格的な交雑育種法によるイネの品種改良が始まった。加藤茂苞(しげもと)をはじめとする技術者たちにより、初めて人工交雑によって生み出された品種が、国立農事試験場陸羽支場で育成された“陸羽132号”である。技術や情報の蓄積で各試験場で続々と新品種がつくられるようになり、現在も流通する品種の多くがこの方法によって生み出された。“コシヒカリ”は、品質と味に定評のあった“農林1号”と、いもち病に強いという特徴があった“農林22号”の交雑によって誕生した。
数々の有名品種を生み出した交雑育種法であるがその成功率は低く、1つの品種ができるまでには数多くの掛け合わせの失敗があるという。温室栽培などで栽培時間の短縮ができるようになった現在でも、新品種誕生には多くの労力が必要であることを忘れてはいけない。
参考文献:
新潟県農業総合研究所 https://www.ari.pref.niigata.jp/kids/
農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1111/spe1_01.html
『コシヒカリ物語』酒井義昭著、中公新書
文:小野塚 游(オノヅカ ユウ)
“コシヒカリ”の名産地・魚沼地方の出身。実家では稲作をしており、お米に対する想いも強い。大学時代は分子生物学、系統分類学方面を専攻。科学的視点からのイネの記事などを執筆中。